先日、私は岡佐紀子氏のジョブクラフティングに関する研修を受けました。研修のテーマは「仕事をよりよく取り組むために、ライフワークとして仕事を捉える土台を構築する」というもので、非常に印象的で有益な時間を過ごしました。今回はその研修の内容と、私自身が得た気づきについてお伝えしたいと思います。
ジョブクラフティングとは?
ジョブクラフティング(Job Crafting) とは、従業員が自らの仕事の内容や関わり方を主体的に調整し、よりやりがいや満足感を感じられるようにする働き方のことです。従来の「与えられた業務をそのままこなす」仕事のスタイルとは異なり、個人が能動的に仕事をカスタマイズ することで、より意味のあるものに変えていくアプローチです。
ジョブクラフティングの3つの要素
ジョブクラフティングは、以下の3つの視点から行われます。
1. タスク・クラフティング(Task Crafting)
仕事の「内容」を変えること。
- 例: 本来の業務に加え、新しいプロジェクトを自主的に立ち上げる
- 例: 効率的な業務フローを考え、単調な作業を自動化する
2. リレーションシップ・クラフティング(Relationship Crafting)
仕事の「人間関係」を変えること。
- 例: 他部署の人と積極的に協力し、新しい視点を取り入れる
- 例: 同僚とのコミュニケーションを増やし、職場の雰囲気を良くする
3. コグニティブ・クラフティング(Cognitive Crafting)
仕事の「意味の捉え方」を変えること。
- 例: 「単なる作業」と思っていた仕事を、「誰かの役に立っている」と考える
- 例: 自分の仕事が会社全体にどのように貢献しているかを意識する
ジョブクラフティングのメリット
✅ 仕事のやりがいが向上する → 仕事の意義を見出し、モチベーションが高まる
✅ ストレス軽減 → 自分に合った働き方を見つけられる
✅ 創造性・生産性の向上 → 業務効率が改善し、新しいアイデアが生まれやすくなる
✅ 組織のエンゲージメント向上 → 従業員が主体的に動くことで、組織全体の活性化につながる
ジョブクラフティングを実践するには?
💡 小さな変化から始める → いきなり大きく変えるのではなく、業務の工夫から
💡 自分の強み・価値観を理解する → どのように仕事を変えればやりがいを感じるのかを考える
💡 周囲と協力する → チームメンバーや上司の理解を得ながら実践する
ジョブクラフティングが注目される背景
- 働き方の多様化(リモートワーク、フレックスタイムなど)
- エンゲージメント向上の重要性(仕事の満足度が企業の業績に影響)
- 個人のキャリア自律(会社に依存せず、自らキャリアを形成する考え方の広まり)
ジョブクラフティングと似た概念
- ワーク・エンゲイジメント(仕事に対する熱意や充実感)
- プロアクティブ行動(受け身でなく、自ら働き方を変えていく姿勢)
- デザイン思考(仕事の課題をクリエイティブに解決するアプローチ)
今回の研修のテーマと進行方法
研修の冒頭、岡佐紀子氏は「キャリアとは、ただの職業選択ではなく、生き方そのものだ」という視点から話を始めました。キャリアを単なる仕事にとどめるのではなく、人生全体をどう生きるかという視点から捉えることで、まず自分自身を全体的に捉え、仕事に対するアプローチが大きく変わるというのです。
研修は、少人数のグループワークを交えながら進行されました。講師の指導の下、まずは自分のキャリアを「全人的な観点」で捉えるために、自分自身の強みや価値観を掘り下げる作業からスタートしました。自分の「こだわり」「得意」「苦手」といった点を言語化し、それをどのように活かしていけるかを考えました。
研修の組み立て—論理的で構築的な進行
私にとって、研修の進行方法が非常に印象的でした。最初は自分の「状態」から始め、一旦、職業の枠を外して自分を客観視することからスタートします。これにより、自分の強みや弱み、価値観をより深く理解することができました。そして、段階を追って「職業人としての自分」、さらには「周りとのコミュニケーションを取る自分」へと捉え方を広げていきます。
この段階的な進行は、非常に論理的かつ構築的で、分かりやすく、効果的でした。最初は自己理解を深め、次に職場での役割を意識し、最後に周囲とのコミュニケーションをどう取るべきかを考える。この順番で自己を見つめ直していくことが、まるで一つの大きな流れとして自然に繋がっていったのです。実際、研修が進むにつれて、自分自身のキャリアに対する捉え方が徐々に変化していく様子を実感できました。
インプットとアウトプットを繰り返すことでの学びの深化
さらに、研修の進行において重要だったのは、インプットとアウトプットを繰り返し行うという点です。全体の講義とグループワークを何度も交互に行うことで、参加者は自分の考えを整理するだけでなく、他の参加者と意見を交換する機会も得られました。この繰り返しのプロセスが、私の学びを深める大きな助けになりました。
たとえば、グループワークでは、他の参加者の視点や意見を聞くことで、自分が気づかなかった新たな視点を得ることができました。その後、全体で共有された意見や気づきを受けて、再び自分の考えを整理し、さらに深めていくという流れが非常に効果的でした。この反復的なプロセスが、単なる知識の吸収にとどまらず、実際に自分の中で活用できる形に変わっていったように感じます。
3つの視点「視点」「視野」「視座」で自分を捉え直す
次に、研修では「視点」「視野」「視座」という3つの視点で自分を見つめ直すことを教えていただきました。
- 視点: 自分が何に注目しているのかを明確にし、自分の仕事やキャリアに対する考え方を再確認する。
- 視野: 自分だけでなく、他者との関係や社会全体との繋がりを意識し、広い視野で自分のキャリアを捉える。
- 視座: 自分のキャリアにおける立ち位置や価値観を確認し、どのような視点で社会に貢献するのかを考える。
これらの視点を意識することで、自分のキャリアをより深く理解し、将来に向けてどのように進んでいくべきかが見えてきました。
自分の気づき—苦手なことを「違う角度から考える」
研修の中で、私は自分が苦手だと感じていることに対する新たな気づきを得ました。私は「コツコツやること」が苦手だと感じていましたが、この苦手な部分を「好奇心旺盛」「なんでもチャレンジする」という視点で捉え直すことができたのです。自分の特徴を違った視点で捉え直すことで、長所に変えることができるという新たな視点がうまれました。
「周りとのつながりの中での自分」を再考
さらに研修では、「自分の役割って何だろう?」というテーマで、周りとの関わりを考える時間がありました。職場のある人を思い浮かべ、その人がどんなことを望んでいるかを考えることで、自分の役割を再確認しました。
私は、職場で一緒に働いているある同僚が「自分のペースで仕事を進めたい」という傾向があると感じていました。そのため、私自身は「自分のやり方で認めてほしい」と思っている部分もありますが、相手のペースを尊重しつつ、自分の方法で進めることの重要性を再認識しました。
例えば、チーム内で進捗状況を報告する際、私が早く進めた部分について他の人に急かすような印象を与えていたことがありました。しかし、相手のペースを理解し、ゆっくり進んでいるときにも自分の進捗を適切に共有することで、相手も安心して仕事に取り組めるようになり、より良い協力関係が築けた経験があります。
進捗状況を共有する重要性
研修の中で、私は「進捗状況をどのように周りと共有するか」という点についても考えることができました。職場で、なかなか進捗状況が共有されないことにやきもきしていた私ですが、まず自分から積極的に情報を共有することが大切だということを再認識しました。
まず、自分から周りに進捗を共有することで、相手もオープンになり、コミュニケーションが円滑に進むと感じました。このような積極的な姿勢が、チーム全体の進行をスムーズにすることに繋がります。
例えば、プロジェクトの進行状況を毎週の定例ミーティングで簡潔に報告するように心がけるなどの取り組みでしょうか。これをやれば、他のメンバーも自分の進捗を共有しやすくなり、問題点や改善案を早期に共有することができるようになるでしょう。
まとめ
今回の研修を通じて、「自分のキャリア」をより基礎の部分から見つめ直し、職場や周りとの関係における自分の役割を再確認することができました。また、「苦手なこと」を違う角度から捉え直すことで、自分の強みに変える方法を学ぶことができました。
自分のキャリアを全人的に捉え、周りとのつながりを意識しながら進んでいくことで、仕事だけでなく人生全体をより豊かにしていけると感じています。今後は、これらの気づきを活かし、職場でのコミュニケーションや自己成長に繋げていきたいと思います。

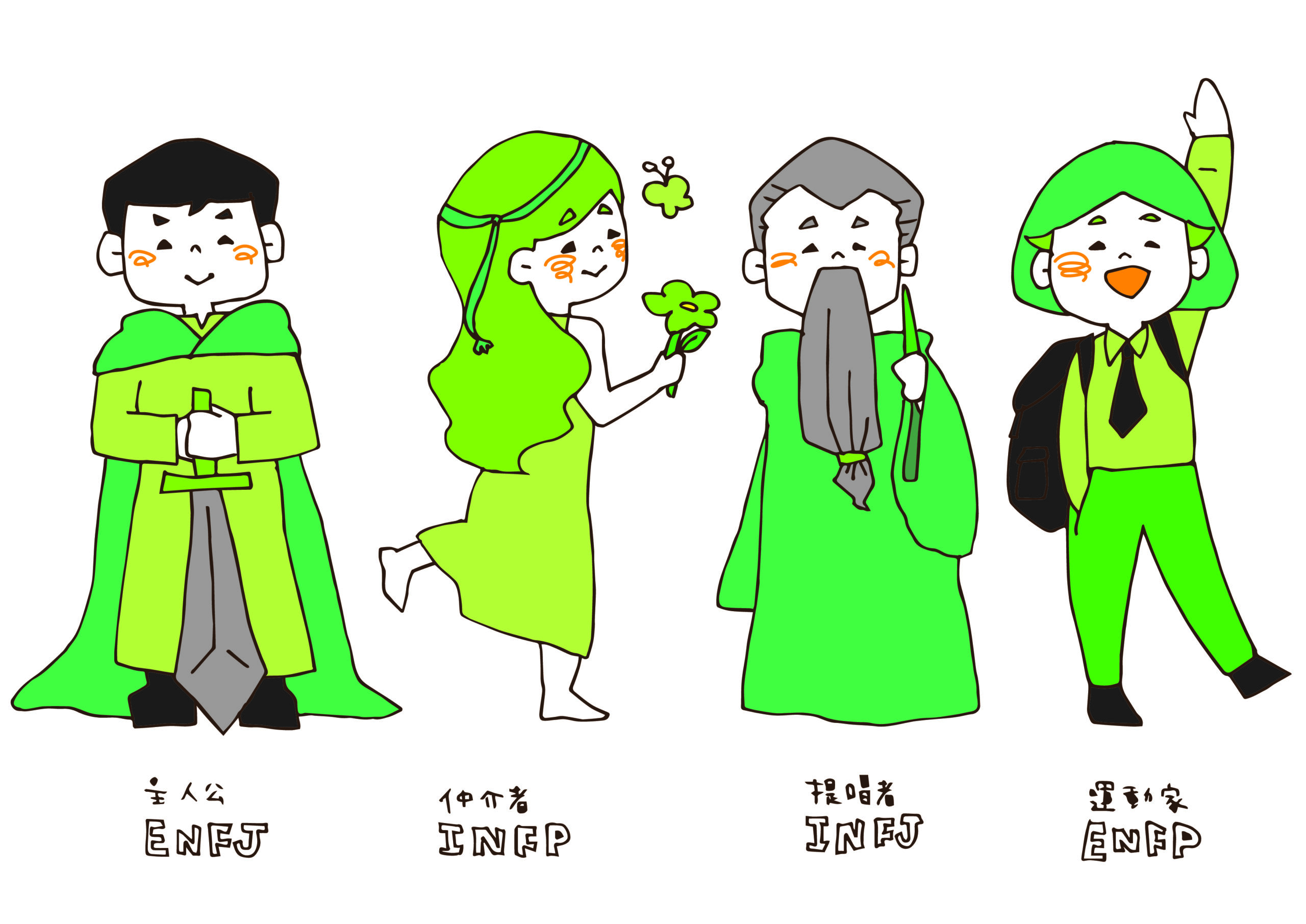

コメント