〜人口減少時代に「新規開店」?〜
最近、ふと目にしたチラシに「鯖江に新しいパチンコホールがオープン!」という告知。
普段であれば気にとめないような情報なのですが、なぜかその日は、目が止まりました。
実は私は、パチンコで遊んだ経験はほとんどありません。
けれど、かつて仕事でパチンコ業界に関わったことがあり、また、家族の中には一時期はまっていた者もいたことから、この業界はどこか気になる存在でもありました。
特別な思い入れがあるわけではありませんが、完全に無関心とも言えない、そんな距離感です。
ところが最近は、近所の小さなホールがどんどん閉店していき、「もう時代遅れなのかな」と感じていました。
そんな中での「新規開店」。しかもチラシによると、大規模なホールで、最新設備も導入されている様子。
人口が減っているこの時代に、なぜ今、新しく開くの?
ちょっとした好奇心から、今のパチンコ業界、特に福井の状況を調べてみることにしました。
◾ 遊技人口は減少中、それでも新しい流れが?
全国的に見ると、パチンコの遊技人口は1990年代の1,700万人から、現在は700万人台へと減少しています。
ホール数もかつての半数以下に。業界全体が縮小する中、「新規開店」という言葉にはやはり違和感がありました。
でも最近は、**若年層を意識した「スマート機」**の導入が進んでいるとのこと。
スマートパチンコやスマートスロットと呼ばれるそれらの台は、玉やメダルを使わず、ICカードで管理されるため、清潔でスマート。
これまでの“昭和的イメージ”から一転、デジタルな遊技体験として再構築されつつあるようです。
◾ 景品交換は、昔ながらの「三店方式」が続く
ただ、スマートになったとはいえ、出玉の交換方式は今も「三店方式」。
店舗で出玉を特殊景品に交換し、それを敷地内外の別の建物で現金に換金するという仕組みです。
法律の建前上は「現金と引き換え」ではありませんが、実態としては今もグレーな運用が続いています。
福井のような地方都市では、駐車場の一角や建物の裏手に、さりげなく交換所があるという形が一般的です。
◾ 小規模店舗が消え、大手チェーンが残った構図
私の身の回りでも、かつては住宅地に小さなホールが点在していました。
けれど近年、それらの多くが静かに姿を消していきました。
一方で、大規模チェーンは生き残っている。
今回鯖江にオープンするのは「DSG」という北陸を中心に展開するチェーン。
これまで福井は「オカダエンタープライズ」、全国規模では「マルハン」が勢力を持って営業しています。
資本力や最新設備、スマート機対応といった体力のある企業だけが、業界内で生き残っている構図が、地方でも進んでいるようです。
◾ おわりに:外から見るからこそ見えてくるもの
私は今でもパチンコを打つつもりはありません。
でも、かつて仕事を通じて見ていたこの業界が、こうして形を変えながらも続いていることに、どこか感慨のようなものを覚えました。
もし近くを通ったときには、新しくできた店舗の外観や、駐車場の一角に佇む交換所の様子を、
「社会の変化の一端」として、そっと眺めてみたいと思っています。
※本記事は個人の視点での調査と感想をもとに書いています。業界や企業の批評を目的としたものではありません。

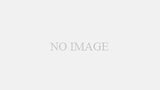
コメント