児童館と高校生の活き活きとした交流の様子については前回記事で書きました。
子どもたちの高校生に対する様子は、年齢が近い安心感、無意識のあこがれ、ちょっと上のお兄さん・お姉さんへの好奇心──こうした心理は、児童心理学の分野でも「ピアエデュケーション(同年代や年齢の近い者からの学び)」として効果があるとされ、国内外を問わず報告されています。
中高年は子どもと距離がある?
しかし、すべての現場に高校生が来てくれるわけではありません。実際、地域の放課後レクリエーション活動の多くは、日中に活動可能な中高年の方々が担い手となっています。
平均年齢50〜60代の方々による、放課後の児童との遊び。正直なところ、最初は「子どもたちは楽しめるのだろうか」と懐疑的でした。けれど、ふたを開けてみれば──
意外にも、子どもたちはよく笑い、よく動き、そしてよく関わっていました。
おそらく、これはレクリエーション協会の方々が「子どもにどう接するか」を普段から学び、実践されている成果なのでしょう。ただ年齢が若いからいい、という単純な話ではない。中高年の方でも、関係性の築き方次第で、子どもと豊かな時間を共有することは可能なのだと実感させられました。
参加者のひとりとして
実は私は、この日の活動では本来、記録係として見守る立場でした。しかし参加児童が少なかったこともあり、気づけば輪に入り、一緒にゲームに興じていました。それはまるで、「遊んであげた」ではなく「遊んでもらった」時間。
そして最後に、自分でも驚いたのですが──
「遊んでくれてありがとう」
そんな言葉が、私の口から自然と出ていたのです。
大人が、子どもにありがとうを言いたくなる。
そんな体験をくれた時間でした。
年齢を越えて、子どもとつながるために
子どもは「わかってくれる人」が好きです。それが高校生であれ、中高年であれ、心を開いてくれる相手には敏感に反応します。若者のエネルギーに勝る「人生経験」や「おおらかさ」もまた、年齢を重ねた人の武器です。
中高年であっても、子どもとの関わりは十分に楽しめるし、深められる。
それを可能にするのは、きっと年齢ではなく「一緒に楽しむ姿勢」と「受け止めるまなざし」なのだと、あの日のレク活動が教えてくれました。


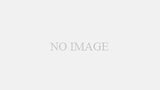
コメント