先日、地域の里山整備活動に協力してくれた高校生たちを撮影する機会がありました。
炎天下のなか、50名近くの高校生——男子も女子も、サッカー部、バスケ部、野球部、射撃部など、様々な部活動のTシャツを着た子たちが、杭を担いで山道を登っていく。
決して高い山ではないとはいえ、荷物を担いでの作業はなかなか大変です。
それでも彼らは、冗談を交わしながら、時に無言で汗を流しながら、一歩一歩、階段を上がってくる。
私は山の中腹の階段でカメラを構えて彼らを待ち受けながら、登ってくる生徒らに「笑顔くださーい!」「目線ちょうだい!」と声をかけると、
みんな、屈託のない笑顔でピースサインを見せてくれました。
爽やかで、まっすぐで、まるで風が吹き抜けるような清々しさ。
撮った写真を後から見返しても、なぜだか自分まで元気が湧いてくる。。。。そんな不思議な感動がありました。
なぜ、若者の姿に心を打たれるのだろう?
不思議なことに、こういう感情は、若い本人たちにはなかなか実感しづらいものです。
彼らにとっては「頑張ること」や「動くこと」は日常の延長線。
その姿が他人を元気づけているなんて、きっと思ってもいないでしょう。
では、なぜ私たち大人は、彼らの姿にこんなにも心を動かされるのでしょうか?
その理由は、脳のしくみや心のはたらきにあります。
たとえば、「ミラーニューロン」という神経細胞が、他人の動きを“自分のことのように”感じさせる働きをしていたり、
「若さ=未来への希望」として文化的・本能的に価値づけられていたり、
あるいは、かつての自分と重ね合わせて、懐かしさとともに“もう一度生きなおす”ような感情を呼び起こしたり——。
いずれにせよ、彼らのまっすぐな姿は、私たち自身のなかにある“生きる力”の種に、そっと火を灯してくれているのだと思います。
若者 × 地域活動は、単なるボランティアではない
この日、彼らが担いでいたのは「杭」だったけれど、
実はもうひとつ、地域の未来そのものをも担ってくれていたような気がしてなりません。
地域活動は、かつては「大人たちのもの」だったかもしれません。
けれど、そこに若者が加わることで、空気が変わり、場が柔らかくなり、新しい視点が生まれます。
それは「若い力を借りる」というよりも、
若い人が地域と出会い、互いに触発し合うという、もっと豊かな循環のはじまりかもしれません。
撮影という形で、その一瞬を記録できたことは、ただの“記録”以上の意味があったように思います。
あの笑顔たちは、間違いなく、地域にとっての光であり、
私自身にとっても、希望を再確認させてくれる光でした。
おわりに:未来は、今ここにいる
「若さ」は、持っている最中にはその尊さに気づきにくい。
けれど、それを目の当たりにしたとき、人はふと立ち止まり、自分自身の中にあった“何か”に再び触れる。
高校生たちのまっすぐな姿に、私は自分がどこかに置き忘れていた「熱量」や「まっすぐさ」を思い出させてもらったのかもしれません。
未来は、どこか遠くにあるわけじゃない。
未来は、今ここにいる——そう思えるような、眩しい時間でした。

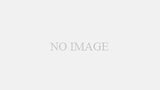
コメント