大人同士で集まって何かをする時、特に料理のような「やり方」が色々ある場面では、その難しさは顕著になりますよね。経験者が集まれば集まるほど、「私はこうやってきた」「いや、こうするべきだ」と意見が分かれ、結局はちぐはぐになってしまう。
そんな時、私は**「リーダー」を決めてしまう**という方法をとることが多いです。よほど非効率だったり、間違っていたりしない限り、その人のやり方に従う。そうすることで、みんなの動きが統一され、ぐっと作業が進みやすくなるからです。
なぜリーダーが必要なのか
なぜ、あえてリーダーを立てる必要があるのでしょうか。
それは、多くの人が集まる場で、全員の意見を平等に反映させようとすると、かえって物事が滞ってしまうからです。特に料理は、段取りが非常に大切です。
- 誰かが仕切らないと「待ち時間」が増える 「誰かがやってくれるだろう」という心理が働くと、誰も手をつけず、野菜が切り終えられるのをみんなが待っている…なんてことになりかねません。
- 「やり方」が違うと効率が落ちる 「玉ねぎはみじん切り」「いや、薄切りがいい」といった意見の対立は、時に作業を止めてしまいます。個々の意見を尊重することも大切ですが、まずは一つの方向へ進むことが重要です。
リーダーを決めることは、個々の意見を無視することではありません。むしろ、**「今回はこのやり方でやってみよう」**と、一つの共通認識を持つことで、全員が気持ちよく作業を進められるための工夫なのです。
リーダーシップは協調性と共存できる
「協調性がない」と評価される私のような人間でも、この「リーダーを決める」というアプローチは意外と有効です。
リーダーとして率先して動くのが苦手でも、「今回はあなたがリーダーね」と役割を振ることはできますし、「このやり方で進めます!」と宣言するリーダーの背中を、「分かりました!」と後押しすることも立派な協調性の示し方です。
自分の意見を通すことだけが「協調性」ではありません。全体の目標を達成するために、自分の意見を一時的に脇に置いて、誰かの決断を尊重する。これもまた、大切な協調性の一つだと私は考えています。
あなたも、大人同士の作業で意見が分かれそうになった時、あえて「今回は誰が指揮を執る?」と尋ねてみてはいかがでしょうか。

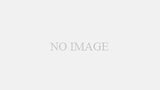
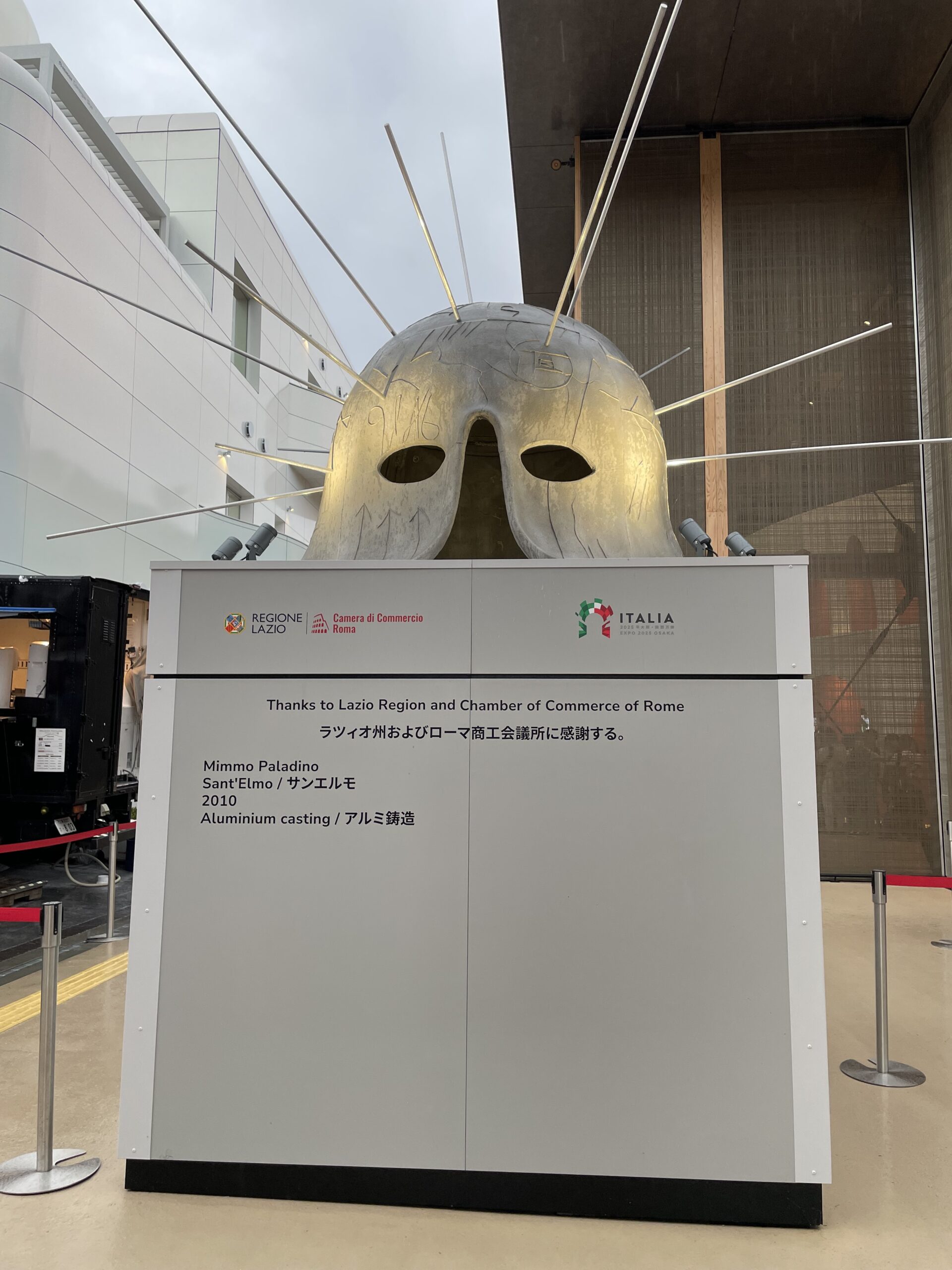
コメント