多文化共生を支える、高校生と社会教育施設の協働
今から3年前、私たちは地元の高校の先生からの相談をきっかけに、協働を始めました。この高校が大切にしている「多文化共生」というテーマを、地域の中でどのように実現していくか。その第一歩として、「そばうち」を地区の方に習い、様々な国籍の方々と高校生が交流する企画をしたのです。
その後も地区の祭りへの参画など、この3年間で、私たちと高校生、そして学校との関係は大きく変化しました。
- 信頼関係の深化:最初は先生方とのやりとりが中心でしたが、今では高校生たちと顔の見える関係ができたことで、「こんなことをやりたい!」という彼らの素直な声が直接私たちに届いたり、企画会議によばれるようになりました。
- 新たなつながりの発見:協働を進める中で、実は以前から地元の事業所と学校が関係を持っていたことを知りました。私たちの取り組みが、そのつながりを改めて見直すきっかけになったのです。
- 地域の輪の広がり:今回のイベントを通じて、地域で働く事業所職員同士や、高校生と大人との間にも新たなつながりが生まれました。点と点が結ばれたり、もとからあった線が太くなったりと、地域のネットワークがより強固なものになっていくのを実感しています。
和菓子で交流
先日開催された「フルーツ大福で国際交流」イベントは、まさにこの3年間で育んできた関係性の証しでした。和菓子を通じて多様な人々が交流する姿は、この協働がもたらした素晴らしい成果の一つです。
大人の役割は「完璧な支援者」ではなく「伴走者」
高校生との協働を通じて、私たちは大人としての関わり方について深く考えさせられました。
イベントの企画や運営は、私たち社会教育施設の職員主導でやれば、もっとスムーズに、そして完璧にできたかもしれません。しかし、それでは彼らがこの取り組みから得るべき学びや達成感が失われてしまいます。私たちは、あえて「手を出さない」選択をしました。
例えば、高校生から斬新なアイデアが出たとき、私たちは安易に「それは難しい」とは言いませんでした。代わりに、「そのアイデア、とても面白いね。でも、たくさんの人に来てもらうためには、どんな風に工夫するとよさそうかな?」と、問いかけるようにしました。彼らが自らの力で課題を乗り越え、より良い企画へとブラッシュアップできるように、そっと後押しするような関わり方です。
私たちは、完璧な答えを与えるのではなく、彼らが自ら答えを見つけるための「ヒント」を提供する伴走者のような存在でありたいと考えています。その結果、高校生たちは失敗を恐れず、様々な挑戦をしてくれました。
協働がもたらす「ウィンウィン」の関係
この協働は、私たちにとって一方的な「支援」ではありませんでした。
彼らがもたらしてくれる若い感性、行動力、そして新しいことへの探究心は、私たち施設職員にとって大きな刺激となっています。彼らを応援することで、私たち自身も新しい学びや活力を得ることができています。
私たちは、これからも彼らの「やりたい」というスモールステップを応援し続け、共に学び、成長していきたいと思っています。この「和菓子」という小さな存在が、これからも多様な人々を繋ぎ、地域に新しい風を吹き込んでくれることを願っています。


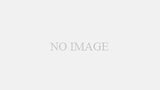
コメント